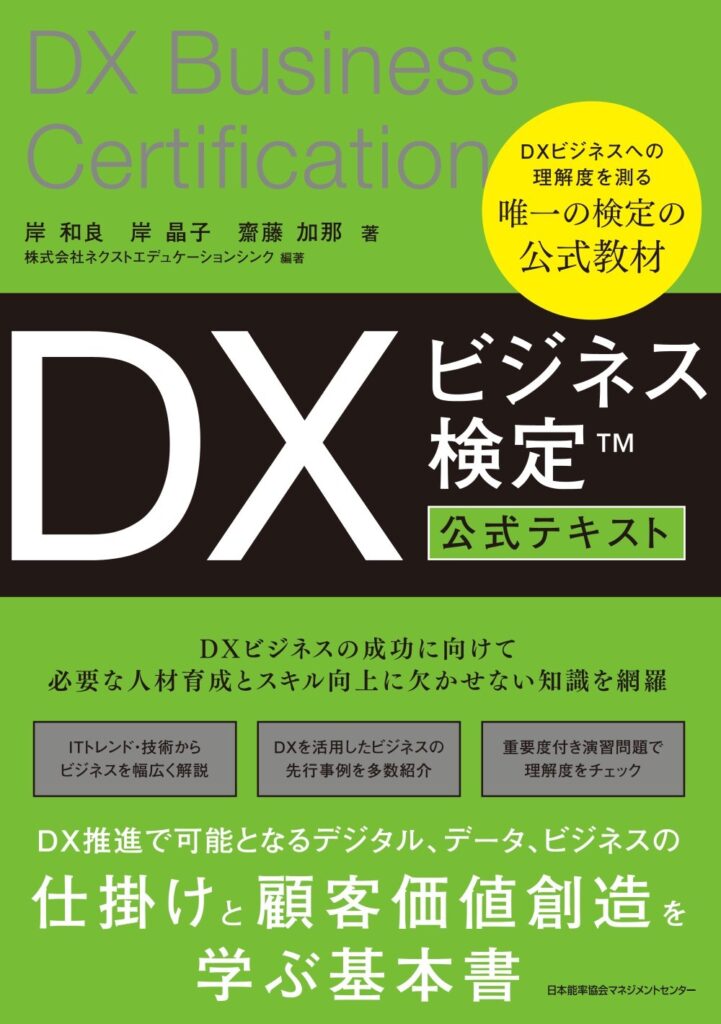JR東海 移動と駅空間をデータでつなぐOMO戦略
前回は「ONIGO」のビジネスモデルから、リアル店舗とデジタルを結ぶOMO型の顧客体験設計について考えました。
今回は、同じく「DXビジネス検定™公式テキスト」第13章「リアルビジネス+デジタル」の事例として、東海旅客鉄道(以下JR東海)を取り上げます。駅と線路、そして新幹線というリアル資産を持つ同社が、デジタル技術を活用してどのように移動体験や駅ナカ価値を再構築しているのかを見ていきます。
「移動」というリアル体験を支えるデジタルUX
JR東海の中心事業は、東京~名古屋~新大阪を結ぶ東海道新幹線です。ここに「デジタルによる利便性」を組み合わせたのが同社のDXの基本となります。
代表的なのが「スマートEX」および「エクスプレス予約」です。スマートフォンやPCからオンラインで予約・変更・支払いを完結でき、改札ではQRコードや交通系ICカードをタッチするだけ。駅で切符を購入、やりとりする手間をなくし、移動そのものの利便性をデジタルで向上させました。

引用:エクスプレス予約 https://expy.jp/top.php?
また、出張や観光など多様な利用目的に合わせて、座席指定・複数人予約・領収書出力などの機能を拡充。これにより、ユーザー側にとっては物理的な移動がデジタルによって“自分で設計できるサービス”へと変化しています。一方JR東海側からするとデータ取得、連携により利用動向を分析することができ、混雑緩和やダイヤ編成にも活かされています。
エキナカDXとリアル空間の再定義
JR東海はリアル拠点である「駅」の価値を、単なる通過点から“目的地”へと変える取り組みも進めています。
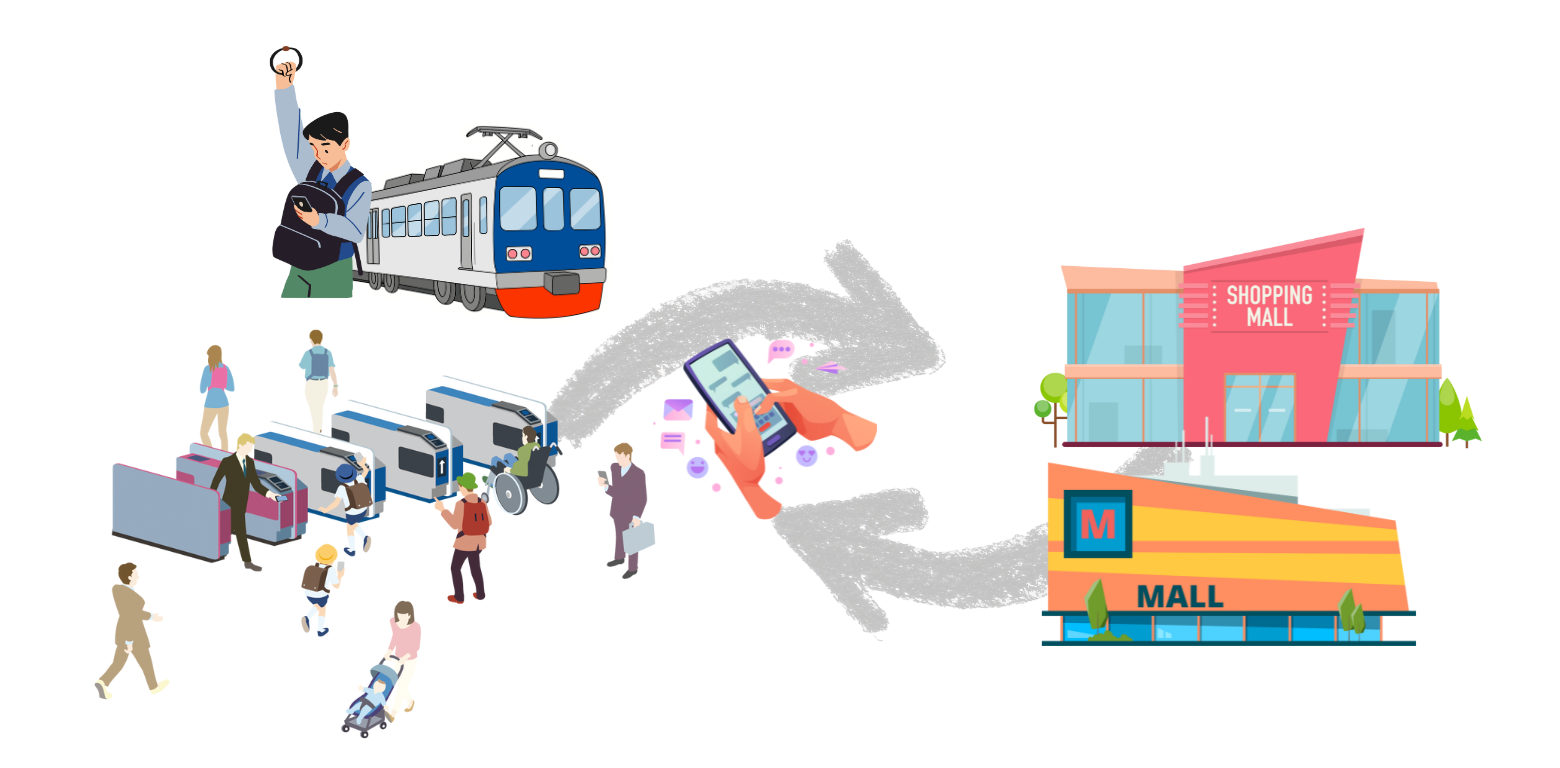
名古屋駅直上の「JRゲートタワー」「JRセントラルタワーズ」などの商業施設は、TOKAI STATION POINTを中心としたアプリ・キャッシュレス決済と連動したエキナカDX事例です。
飲食・物販・ホテル・オフィスが一体となる複合空間において、スマートフォンによる事前オーダーやポイント連携が進み、購買データと移動データを総合的に分析できる仕組みを構築。リアル空間での顧客行動をデジタルで可視化し、時間帯別の来店傾向や購買動線の最適化に役立てています。
ここには、鉄道事業と商業事業を分けず、「移動・滞在・購買」を一つの顧客体験としてデザインするという思想があります。
鉄道会社にとって輸送収益だけで採算を取ることは年々難しくなっています。人口減少とテレワーク定着によって乗車人員が減少する中、駅と線路という広大な土地資産をいかに再設計し、収益化するかが経営課題となっています。
JR東海は、このリアル資産を「移動インフラ」から「商業・滞在・データ収益の拠点」へと転換しようとしています。エキナカアプリやポイント連携、モバイルオーダーなどのデジタル施策によって人の流れを駅に引き寄せ、データを基盤とした収益化を進めているのです。これにより、鉄道運賃に依存しない新たな事業ポートフォリオを築きつつあります。
MaaSと観光データ連携によるエコシステム化
近年、JR東海は交通を軸としたMaaS(Mobility as a Service)にも注力しています。観光地での二次交通(バス・レンタカー・シェアサイクルなど)をデジタルで統合する実証を進め、アプリ上で経路検索から決済までを一元化する仕組みを構築しようとしています。
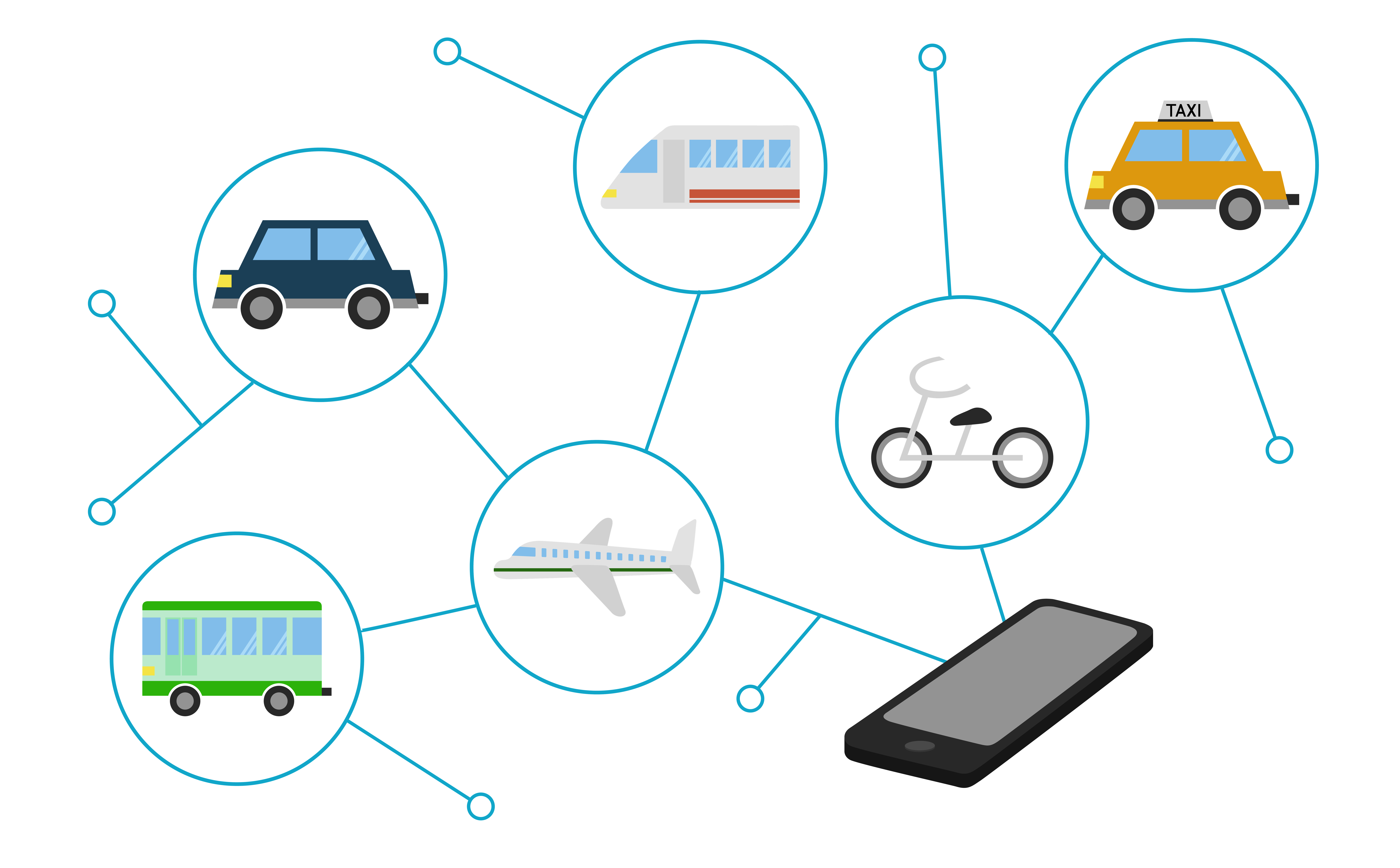
地域観光DXの一環として、沿線自治体や観光団体とも連携し、乗車や宿泊などのデータを組み合わせて地域観光の可視化を目指す取り組みが各地で進められています。
現時点では一部の地域での実証段階ではありますが、今後は交通・観光・購買データを連携し、地域イベントやプロモーション設計に活かす仕組みの実装が期待されます。
DXビジネスモデルとしての意義
JR東海のDXは、単にチケットをデジタル化しただけではなく、リアルな移動体験そのものをデータドリブンに再設計した点に価値があります。
スマートEXによるUX向上、駅商業施設のエキナカDX、MaaSによる移動・観光の統合設計。それぞれが顧客接点を分析、拡張し、リアル事業の競争力を高めています。
これは「リアルを軸にデジタルを重ねる」第13章のモデルであり、デジタル商材系やマッチング型とは異なり、現地・現物の価値を中心に据えたデジタル戦略です。
リアル資産の強みを持つ企業こそ、デジタルによるUI/UX拡張が経営の新たな成長源になる。その好例です。
まとめ
これまでの連載で見てきたように、タイミーは「時間と仕事」、minneは「クリエイターとファン」、U-NEXTは「ユーザーとコンテンツ」、スタディサプリは「学習者と教材」、ONIGOは「生活者とリアルなモノ」を結びました。
そしてJR東海は、「移動と体験」「駅と生活」をデジタルで結ぶ存在といえます。
切符からアプリへ、駅から移動プラットフォームへ。デジタルがリアルに置き換わるのではなく、リアルの価値をデジタルで拡張する。それがリアルビジネス+デジタルのかたちです。
次回までの宿題
次回は14章「リアルビジネス」の事例としてCAINZを取り上げます。リアル店舗を軸にOMOやSPA(製造小売)戦略をどのように組み合わせているのか、リアルビジネスの強みをどう活かしているのかを、一緒に考えていきましょう。
<vol.8に続く>

DXビジネスアンバサダー
岸 晶子
きし あきこ
都市銀行勤務後、出産を経て専業主婦に。3人の子育てが一段落した際にデジタルリスキリングを実施。その経験を活かしDXビジネス教育に関するコラム記事や大学向け教材作成などを手がける。